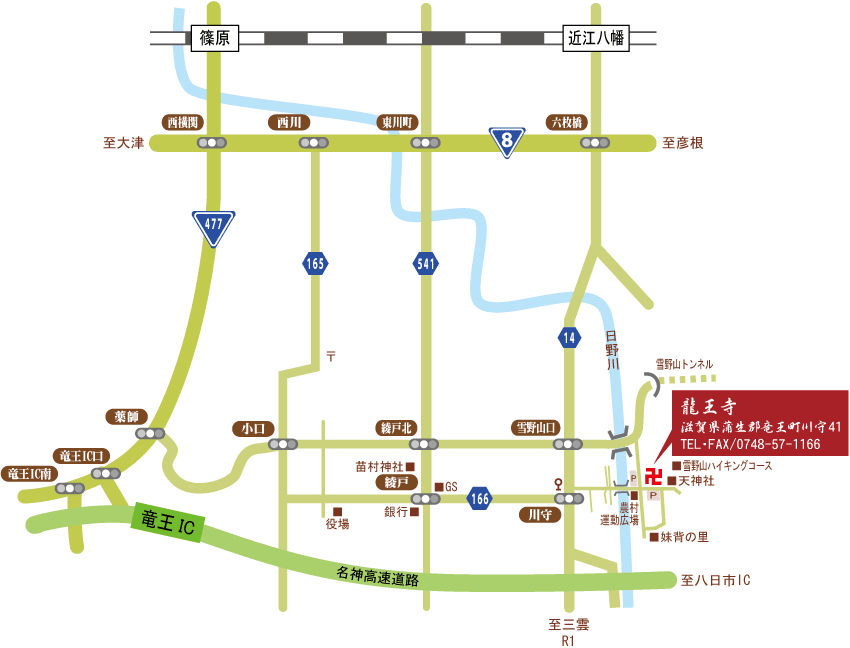history
ご由緒
飛鳥時代から続く名刹
いいね
0
りゅうおうじ
滋賀県蒲生郡竜王町
江戸時代に再建された本堂の外陣には、公遵法親王によって『醫王殿』と記された額が掲げられている。毎年中秋の名月の日に喘息封じの祈願である「へちま封じ」という行事が行われている。 この日には普段は閉ざされているお厨子が開かれ、平安時代後期に造られたという御本尊・薬師如来像を拝することができる。厨子の左右には日光菩薩立像・月光菩薩立像をはじめ、御本尊と同じタイミングで造立されたと伝わる地蔵菩薩立像や観音菩薩立像が安置されている。さらに、平安時代に造立されたと考えられている阿弥陀如来坐像もおまつりされている。
御本尊がおまつりされている厨子を中心に左右に6躯ずつ十二神将立像がおまつりされている。甲冑に身を固めた武将の姿で表されている⼗⼆神将立像の頭上には、それぞれ⼗⼆⽀の動物を頭に載せており、この形式は鎌倉時代以降に造立された十二神将立像の特徴であるという。龍王寺でおまつりされている十二神将立像は鎌倉時代に造立されたと考えられており、12躯すべてが揃っている点が貴重であるとして国の重要文化財に指定されている。
鐘楼につるされている梵鐘は奈良時代から平安時代に造立されたと考えられている鐘で、国の重要文化財に指定されている。この鐘には小野時兼と美和姫の悲恋の物語が伝えられている。光仁天皇の御代、小野時兼は病にかかり、この地に赴き龍王寺の御本尊である薬師如来に祈願をしたという。すると、小野時兼の病は癒え、さらに美和姫という美しい女性と出会い仲睦まじく幸せに3年間の月日を共に過ごしたという。しかしながら、ある日突然美和姫は小野時兼に対し別れ話を持ち出し、『私は人間ではなく、雪野山の近くの沢の主である。もし私を思ってくれるのであれば、その沢に来れば本当の姿を見せよう。』と言い、百日百夜、絶対に開けてはならないという約束とともに玉手箱を渡した。小野時兼は最初は懸命にこらえていたが、次第に恋慕がつのり美和姫と出会うために沢へと赴いた。しかし、小野時兼がその沢で見たのは十丈ほどの恐ろしい姿をした大蛇であった。 そのあまりの恐ろしさに小野時兼は逃げてしまい、九十九日目にして玉手箱を開けてしまった。すると箱の内から紫雲とともに梵鐘が出現したという。小野時兼はこの出現した梵鐘を龍王寺に寄進をし、その梵鐘が現在まで伝えられている龍王寺の梵鐘であるという。この伝承のため龍神をまつる鐘『龍鐘』としてよく知られている。鐘の上部にある龍頭を白い布で覆い、これを外すと大雨が降ると言われている。
学生レポート

京都大学大学院文学研究科修士2年
ご由緒
参拝情報